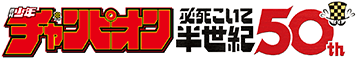2019.10.03
“学校怪談” 高橋葉介先生
レジェンドインタビュー
傑作ホラーショート集として大人気を得て、その後、強烈なキャラたちの活躍で長編と化した「学校怪談」。
その作者・高橋葉介先生に本作の成り立ちや、九段九鬼子の貴重な誕生秘話などを語っていただいたぞ!!

担当さんになんの相談もなく描いちゃったんです
『恐怖新聞』(つのだじろう先生 ‘73年~‘75年)、『エコエコアザラク』(古賀新一先生 ‘75年~‘79年)など、これまで数多くのホラーマンガの傑作を送り出してきた週刊少年チャンピオン。その90年代を代表する作品が、今回取り上げる高橋葉介先生の『学校怪談』(‘95年~‘00年)である。まずは高橋先生に、『学校怪談』が始まったいきさつからうかがった。
「お話をいただいてから、まとまるまでずいぶん時間がかかりまして、おそらく一年くらい決まらなかったんじゃないですか。それで編集長がしびれを切らして、『いいから、もうタイトルは「学校怪談」で! ページ数は10!はいスタート!』ってことではじまりました。
それまでは、西部劇でいこうか、みたいな話もあったんですけど、今思うと描かなくてよかったと思います(笑)」
5年におよぶ長期連載が転機を迎えたのは、連載2年目のこと。それまでは中学生・山岸涼一の周囲で起こる怪奇現象を描く、一話完結のホラーショート・ショートのスタイルだったのだが、単行本第6巻の1話目にあたる第91話(今週号にて再掲載)からは、新たに登場した涼一の担任教師・九段九鬼子を中心とした、ゆるやかな連続ドラマ形式に変更。連載途中での方向転換自体はそれほどめずらしいことではないかもしれないが、なんとこの路線変更は編集部に相談することなく進められたというのだ。
「約一年ちょっと、毎週一話読み切りでやってたんですけど、さすがにちょっと厳しくなってきて、これはキャラクターものにしないとやっていけないと思って、担当さんになんの相談もなく描いちゃったんです。それで(91話の)原稿を渡したら、担当さんからは『あ、おもしろい先生キャラが出てきましたね』という反応が返ってきて。次のときは『あれ、また出てきましたね』。その次は『これ、三部作ですか?』。さらにその次で『ちょっと! これ、続くんですか!?』。そこで初めて気がついたらしい(笑)」

霊感があったら、描けなかったと思いますよ
高橋先生のデビューは1977年。マンガ家を目指すようになったきっかけもたずねたが、意外にも「マンガ家になりたい!」と強く決意したことはないという。
「マンガ家という職業に憧れたことはないんですけど、ずっとマンガを描いていられたらいいなとは思っていて、そしたら職業にするしかないんですね(笑)。あの頃、コミケがあったら、たぶん普通に会社に勤めて、年に二回だけ、おおいに盛り上がってたかもしれないですね」
マンガ研究会に所属していたという大学時代には、少年チャンピオンの発行元である秋田書店にマンガの持ち込みに来たこともあるというが─。
「秋田書店を選んだ理由ですか? アイウエオ順です(笑)。でも、そのとき原稿見てもらった編集者がすぐ辞めちゃって、話が立ち消えになっちゃったんですね。だから、電話帳で調べて次の会社に行きました」
その会社、朝日ソノラマから刊行されていた雑誌に短編『江帆波博士の診療室』が掲載されたことで、高橋先生はマンガ家としての道を歩み出した。以来、その幻想的かつ詩的な世界観とシニカルなユーモアのセンスで多くのファンを魅了し続けているのだが、それと同じくらい人気が高いのが、毛筆で描かれた高橋先生の独特な絵のタッチである。先生はいったいいつ頃から、筆を使って原稿を描かれるようになったのだろうか。
「同人誌を描いてた頃から毛筆を使っています。主線は筆で描いて、あとはペンですね。髪の毛とかも筆です」
筆を使うようになった最大の理由は、ペンと紙との引っかかりが気に障るからだと言う。
「カリカリするのが嫌なんですよ。筆の《丸い》感じが気に入ったんじゃないのかな。インクも、マンガ用のものでなく墨汁で描いています」

高橋葉介●たかはし ようすけ
毛筆とペンを併用する特徴的な執筆スタイルで、ニューウェーブ漫画家として知られるようになり、数多くの作家に影響を与えた。「学校怪談」の他には「夢幻紳士」や「怪談少年」などの代表作がある。
続けて、アイデアの出し方を質問したところ、苦笑とともにこんな答えが返ってきた。
「それがわかれば苦労はないです(笑)。机の前でやることもあるし、そうでないこともある。だいたい、みなさんそうでしょうけど、いきなり関係ないこと─部屋の掃除しだしたり、風呂の掃除したりと─さんざん七転八倒して、ああもうだめかと思ってるときにパッと浮かぶ、というのがアイデアですから。本当に、これをやれば必ずアイデアが出る、という方法があったら教えてもらいたい(笑)。
アイデアの出し方って、マンガ家さんによって違うんでしょうけどね。集中して、お坊さんの修行みたいにしてひねり出す人もいるし、バーっと遊んでから、こもるっていうメリハリ型の人もいるし、もちろん散歩しながら考える方も多いですよ。楳図かずお先生もそうでしょうね。街を歩いていると、よくお見かけしますから。ただ、どうも楳図かずお先生を見るとハッピーなことがあるという噂があるらしくて、女子高生が楳図かずお先生と肩組んで写真撮ってたりする(笑)。この御方をなんとこころえる!と言いたくなるけど、女子高生は無敵だからなあ」
ちなみに、これまでに幾多の怪奇マンガを手がけてきた高橋先生だが、霊感そのものはお持ちではないとのこと。
「一切ないです。たまに心霊写真みたいなものを送ってくる人がいるんだけど、そういうものは送ってこないでください。怖いから(笑)。
でもね、逆に霊感があったら、描けなかったと思いますよ。嘘を描いちゃうことになるじゃないですか。まあ(マンガ表現というものそれ自体)嘘なんですけど、でも、嘘だとわかって嘘を描くのと、実際の体験を誇張して嘘にするのとでは、やはりちょっと違うと思うので、むしろ霊感がなくてよかったと思っています」
夢のちからはすごいなって思うし、
夢を与えるようなマンガがいい
さらに、「もしも、チャンピオンで新作を描くとしたら、どんな作品を描きますか?」という質問には、「週刊誌はもう体力的に無理ですよ(笑)」と笑いながらも、こう答えてくれた。
「そういう現実的な制約はひとまず脇においておいて、仮定の話でもいいのであれば、《博士と助手もの》がいいですね。もともとデビュー作も《博士と助手もの》みたいなものだったし。
昔の少年誌って、わりとそういう《博士と助手もの》が多かったんです。鉄腕アトムのお茶の水博士とか、鉄人28号の敷島博士とか。必ず白衣を着て、ちょっと偉そうで、なんの研究をしているのかわからないような博士がどの雑誌にも載っていたんですね。それってきっと、あの頃の子供が考える、えらい大人を具体的な形にしたものなんですよ。昔の子供って、本当に素直にあこがれましたからね。《末は博士か大臣か》という言葉もあったくらいだし。『大きくなったら、えらい人になるんだ』と、誰にはばかることなく言えた時代だったじゃないですか。まあ、そういうふうに親に洗脳された面もあるんだけど(笑)。
もちろん今の子供も、野球選手とかサッカー選手とかなりたい職業はあるんでしょうけど、だいたい小学校の高学年くらいで諦めて、当たり障りのないことを言い出すわけじゃないですか。でも、ほんのごく一部だけど、ずっと諦めない子供もいるんですね。子供の頃、ウルトラセブンにあこがれて、実際に宇宙にまで行っちゃった宇宙飛行士の古川聡さんみたいな人もいるんだから、夢のちからはすごいなって思うし、そういう子供に夢を与えるようなマンガがいいですね」

最後に、週刊少年チャンピオン創刊50周年のメッセージをいただいた。
「50年も続いた、老舗の本にかかわれて光栄でした、ということにつきますね。これからさらに百年二百年と続きますように─と、そういう月並みな祝辞でお茶を濁させていただいて(笑)。……やっぱりね、これから紙の本にとってますます厳しい時代になっていくんでしょうけど、でも、本が好きな人は、きっと好きなままのはずだし、万人受けを狙うよりも、どうしてもチャンピオンじゃなきゃ、という人に向けて、これからも作っていってもらえればと思っています」