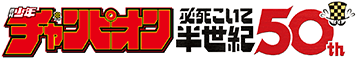2019.01.24
“恐怖新聞” つのだじろう先生
レジェンドインタビュー
オカルト漫画の偉大なる先駆者!!「恐怖新聞」の怪匠が降臨!!
黎明期のマンガ界に火を灯した…伝説的なエピソードが今語られる!!

怖い話がヒットするなんて、誰も予想してなかった
つのだ先生が、日本初のオカルトマンガ『恐怖新聞』を描かれるようになったきっかけを教えてください。
「その話なら、『恐怖新聞』よりまずは『亡霊学級』(73年)なんだな。オカルトマンガの最初のものは『亡霊学級』。まず、編集者は壁村(『週刊少年チャンピオン』二代目編集長・壁村耐三氏)です。伝説の男ね。あいつがね、夏の増刊だったか、「なんか描け」と(仕事を頼んできた)。こっちは手一杯だと言っても、動かない。それこそ壁のように動かないんだ。とにかく「なんか描け」だから、「じゃあ、本当に好きなことを描いていいんだな!」とことわって『亡霊学級』を三作描いたんですよ。
それがドーンといっちゃった。そんな怖い話がヒットするなんて、誰も予想してなかった。そしたら、とたんにすっ飛んできたのが『少年マガジン』の宮原(講談社『週刊少年マガジン』第四代編集長・宮原照夫氏)だ。「あれをやりたかったんです! あれでいきましょう!」(笑)。それで始まったのが『うしろの百太郎』(『週刊少年マガジン』73年~76年連載)。
その当時、ぼくは心霊の研究をやっててね。心霊科学協会っていう、マイナーな団体だけど、そこへ顔を出したりしていて。そこは霊魂を系統だてて説明しようじゃないか、という(趣旨で設立された団体)。だから、守護霊だとか背後霊だとか地縛霊だとか、そういうネーミングは、そこの団体から出てきた言葉なんだ。今はもう一般的な言葉になっちゃってるけどね。悪いけどありゃア俺の手柄だからね」

そもそも、つのだ先生が心霊やオカルトに興味を持つようになったきっかけというのは?
「UFOを実際に自分の目で見て、それ以来、そういった不思議方面を、マンガにするとかじゃなくて趣味で調べてたのね。
あれは昭和三十三年(1958年)の、確か六月くらいだったと思う。ちょうど両国橋を歩いてたら、向こう側にいた人が「あれはなんだ!」と空を指さすから、見たら、オレンジ色に光ってる円盤、フライング・ソーサーだな、それがこのくらいに(と言いながら両手を広げて)見えてる。しかも、それが自分から発光してるのね。
最初は太陽かと思った。それほど明るかった。でも、太陽は別にあった。月も別にあった。太陽でも月でもない。これはもう完全にUnidentified Flying Object、UFOですよ。それを見て、「あ、科学では説明できないことが、この世の中には絶対にあるんだな」と。
それから調べ始めたんだけど、当時はアメリカでさえ円盤騒ぎが始まってまだ二、三年目くらいだったんですよ。当然、日本に資料なんかまったくないわけ。調べるんだったら洋書を探して、と思うけれども、俺は残念ながら高校時代、英語が1だったからさ(笑)。英語じゃあ取り組めないんです。そこで、俺が調べることのできる不思議なものはなんだって考えたら、日本にずっと昔からある怪談、怪(け)だろう、と。そういうものを調べていったところ、さっき話していた心霊科学にたどり着いたんだね」
そのタイミングで仕事の依頼が来て、日本初のオカルトマンガである『亡霊学級』という短編が誕生したわけですね。そうしたら、そのヒットに着目したライバル誌でなぜか連載が決まってしまった、という(笑)。
「そうです。向こう(『マガジン』)は「これがやりたいんだ!」と気持ちのいいことを言ってくるから、こっちもどんどん乗り気になってきてさ。それでドーンと人気が出たのが『うしろの百太郎』なんだけど、そうしたらムクれたのが壁村ですよ(笑)。「ウチでもオカルトものをやれ」って。
でもね、実はその時、俺はすでに『チャンピオン』で『泣くな!十円』という別のマンガを連載(71年~73年)してたんだよ。俺自身、ずごく気に入ってた作品だったし、人気だって常に二位か三位に入ってたんだ。それをやめて、オカルトものをすぐにやれって言うんだね。もちろん俺は「『泣くな!十円』をやめたくない」と抵抗したんだけど、壁村は「じゃあ二本連載しろ」(笑)。めちゃくちゃですよ、あの男の強引さは」

つのだじろう
1936年7月3日生まれ。1955『漫画少年』に「新桃太郎」でデビュー。
トキワ荘グループの一員。
1973年に週刊少年チャンピオンにて
「恐怖新聞」の連載を開始。
以後、心霊研究家としても活躍するようになる。
『マガジン』で連載しながら、『チャンピオン』では二本連載しろ、と(笑)。今だったらとても信じられない話ですよね。
「その頃だって信じられないよ! 当時だって俺、結構いいポジションのマンガ家だったからね、「嫌だ」って言ったら普通は嫌で通るんだけど、それを押しのけて入ってくるのが壁村なんですよ。しかも、毎日のように押しかけてくるんだアイツ(笑)。仕事にならないんだよ。
仕事をめいっぱい抱えて、他社の編集者が常に数人、詰めている状態でさ、壁村にまで時間をとってたら、もうなにもできなくなっちゃうわけで、結局、『泣くな!十円』をやめて、泣く泣く『恐怖新聞』を描くことになったわけです(笑)。
だけどね、実際の話、本気で俺が描いたのは、『百太郎』もそうだし『恐怖新聞』もそうだけど、わずか二年くらいのものなんだよ。連載期間は二年くらい。二年で「もう嫌だ」って言ってやめたんだ、両方とも」
もっと長く連載が続いていたような印象があったんですが、意外と短かったんですね。
「おもしろいんだよ。作家って、それぞれ癖というか個性があって、トキワ荘の連中だってみんな癖が違うわけですよ。「なんか思いついた!」「それ描け!」って言って描き始めて、ラストは尻切れトンボになるのが石森(石ノ森章太郎)。俺とか我孫子(安孫子素雄=藤子不二雄Ⓐ)はね、手をつけたら一生懸命やるんだけど、二年も描くともう嫌になっちゃって、違うことをやりたくなっちゃうタイプ。藤本(藤本弘=藤子・F・不二雄)なんかは、ずーっと同じパターンを延々積み重ねていくわけだ。だから、本当は藤本のやり方のほうが(少年マンガの)本道なんだろうと思うけど、でも、逆に、俺みたいにあっちこっち手を出したおかげで、マンガのジャンルがいろいろできたっていう面もあると思う。ジャンルそのものがなかった時代からやってるからね。
自慢する気はまったくないけれども、ヒットしてるやつのルーツを探れば、みんな俺のところに来ちゃってるかもしれないな」
オカルトに限らないわけですよね。
「限らない。あらゆるジャンルの根本。たとえば少女マンガっていうジャンルだってなかったわけだからね。
少女漫画の始まりっていうのは、俺とかちばてつ(ちばてつや)とか、ほとんど男の作家が描いてたんだよね。我々より前にあったものは挿絵。中原(中原淳一)とかね。それを後世の人間が(現在の少女マンガのルーツとして)結びつけちゃうわけだよね。そうじゃないだろって。知らねえ奴が物を書くと、いろいろ間違いが多い、っていう話だね。話がそれたな。『恐怖新聞』に話を戻すか。どこまで話したかな」
絵を華やかに見せるために新しい表現にチャレンジ

恐怖新聞』はストーリーも多彩ですが、絵による表現のほうも、それこそ点描あり抽象画風タッチあり浮世絵風タッチありと、バリエーションが実に豊富です。そういった、絵についてのこだわりを聞かせてください。
「分析されたら、なにかわかるのかもしれないけど、自分としては意識せずやってたよね。
あ、でも、こういう(カラー原稿でキャラクターの)髪の毛を赤くしたりとか、緑色にしたりとかは俺が始めたんだからね(単行本『恐怖新聞』第一巻表紙絵を参考のこと)。それまでは、髪の毛はみんな黒く塗ってたんだから。今ではもうみんな使ってるテクニックだけど」
なぜ、そのように描こうと思われたんですか?
「とくに表紙では、(メインキャラの)髪の毛の色を黒って決めて塗っちゃうと、占めるスペースが大きすぎて、絵が華やかにならんわけだよ。(暗褐色は)どうしても引いて見えちゃう。これなんかもそうだ(単行本四巻表紙を示して)。暗い色調で塗られたポルターガイストは後ろに置いたほうが、(前面にいる主人公の)キャラクターが立つんだね」
個人的には、単行本五巻の表紙が最高にかっこよかったです。野球場と丑の刻参りという構図にしびれました。
野球はお好きだったんですか?
「結構やってたよ。トキワ荘で。チーム作ってね」
ポジションは?
「セカンドくらいがいちばん好きだったんだけど、ピッチャーもずいぶんやらされたね。我孫子がキャッチャーやって。チームの名前はなんて言ったっけ、コミックスじゃねエな。忘れた。屁番号っていうのだけは覚えてる。背番号じゃなくて屁番号、ケツに番号がついてるんだ(笑)」
チームの中で上手だったのは、どなたですか?
「いないいない。草野球もいいとこ。石森なんか下駄履きでやってたんだから(笑)。ちばてつやが対抗してチーム作って、そことは結構、試合やってたよ。哲学堂(東京都中野区にある公園)のグラウンド借りてね」
火を起こす前にはまずは焚き木を集めておくこと

話を『恐怖新聞』に戻しますが、連載中に読者からの評判で覚えているものはありますか?
「そんなものはない。読者の声なんて、せいぜいチャンピオンの巻末にある読者ページを見るくらいしか暇がないよ」
ずーっと仕事場にこもって描かれていたわけですからね。
「そうよ。我々はいわば、製造機械なわけだからさ。七十二時間一睡もせず、っていう仕事をさせられてたんだぜ」
七十二時間ですか!?
「そうだよ。丸三日、一睡もしない形だよ。それがずーっと続いて、「もう持たないから、三十分でいいから寝かせてくれ」って言いながら描いてたんだから、俺ら世代は。
だから、「自作を分析してくれ」と言われても困るんですよ。そんなの覚えてないし、覚えてる暇もない!」
そうしたハードな締め切りに追われながら描いた『恐怖新聞』ですが、毎回違うテーマ、違うネタが取り上げられていて本当に驚かされます。当時のタイトなスケジュールに追われながら、いったいどのようにして新しいネタを仕入れていたんですか?
「これはね、師匠の島田啓三(00年~73年 代表作に『冒険ダン吉』など)からよく言われた言葉なんだけど、「いざ、その場になってからジタバタするような人間はダメだ」ってことだね。連載を持つんだったら、その前からしっかりと準備をしておく。
火を起こす前には、まずは焚き木をたっぷりと集めておくことが大事なんだ。
そして、いったん火をつけたら、次々と焚き木をくべて、今度は燃える炎を絶やさないようにしなきゃならない。俺の場合、オカルトっていう、誰も手をつけてない焚き木が山ほどあったわけですよ。だから、『恐怖新聞』はメジャーな作品になったんだろうと思うし、逆に焚き木をみんな俺が使っちゃったもんだから、あとの連中は燃え残りの焚き木でやりくりして、みたいなことになっちゃってるんだろうと思うね」
それこそ背後霊とか地縛霊といった名称もそうですし、マンガの中に出てくる小道具のタロットカードや、丑の刻参りの藁人形など、子供の頃に読んだ『恐怖新聞』ではじめてその存在を知ったものがたくさんあります。
「そういうものも焚き木のひとつ。そのほかにもパリで三日くらい古道具屋や書店を歩き回ったり、アメリカの、観光地でもなんでもない土地でやった心霊研究者の集まりに参加してみたりとか、ずいぶんいろいろなことをやりましたよ。焚き木っていうのは、そういう取材も含んでいるわけです。
結局、ぼくの仕事っていうのは──『恐怖新聞』も含めてですけど──足で取材する、っていうことをベースにしてるんですよ。それがいちばん裏付けとして強くなるのね。経験したこと、体験したことを描くのがいちばん強い。それは現代の作品にも言えることなんじゃないのかな」
描かなきゃいけないから描いちゃったんです

『恐怖新聞』の連載中に発生した最大のピンチはなんですか?
「眠らせてもらえなかったことだな(笑)。それはともかく、個々の作品について、どうのこうのっていう問題はない。結局、どの作品もとにかく忙しい中で描いていた、ということだ。
俺がやっていたのは、手では『恐怖新聞』のコマ割りやりながら、頭では「うしろの百太郎」のアイデアを考えて、というようなやり方。ところが、二日三日徹夜になってると、意識が混ざってくるわけだ。そうすると『恐怖新聞』の中に、無意識に百太郎を描いちゃったりするわけですよ。そういうときでも、その原稿用紙一枚を無駄にするっていうことはできないわけで、そのコマだけを切り貼りするっていうやり方をするようになった。原稿用紙の裏に紙を当てて、カッターナイフの刃を斜めに入れて、下から紙を裏打ちするっていうやり方。あの技法も、俺が最初にやったものだし、あとはスクリーントーンも最初に使ったの俺だからね」
本当ですか!
「マンガ用のスクリーントーンっていうものはそもそも存在しなかったんだから。あるのは建築図用のやつだけ。ここは屋根だとか畳だとか、つまり昔でいうところの“地紋”だね。それを俺が画材屋で見ッけてマンガに使うようになったら、トキワ荘の連中がスグ食いついてきたわけだ。「お前! ここどうやったんだ! 教えろ!」って。それで、トキワ荘の連中が使い始めたら、すぐ次の週には手塚(手塚治虫)さんが使い始めてた(笑)」
先生の場合、たとえば服の柄のためにスクリーントーンを使うだけじゃなくて、主人公の心理状態を表すカットでも大胆にトーンを使われていますよね。とても斬新な使い方だと思います。
「でも、自分としては、それが斬新だとか思ってやってるわけじゃないわけ。使わないと締め切りに間に合わないから使っただけ。それがただ、はしりだったというだけのことじゃないの。
今のマンガの技法っていうのは、その大半が手塚さんとトキワ荘の我々で作ったものなんだよ。なかには廃れてしまった技法もあるけど、その中のいいところが今のマンガ家たちにも残ってる、ということだろうな。
あとはもう、なにもわからんね。とにかく寝ずに、一生懸命描いた、というだけだね。そこを分析しろって言われても──」
困る?
「と言うより、答えがない」
頭で考えた、というよりも、なにかが降りてきた、という感じですか?
「降りてきたと言ってしまえば、(創作物というものは)全部、降りてきたものじゃないか。ただ、寝ないでやってるとき、ふと自分が“描かされている”という意識になったときはあるね。
背後にいるものたち……守護霊とか背後霊とかが、俺を成功させようとして、いろいろとやってくれたと、そういう感じはありましたね。作家として物語を作り出すとか、そういう感じじゃないんですよ。描かなきゃいけないから描いちゃったんです」

そのような感覚をお持ちになるのは、『恐怖新聞』だけですか? それとも、ほかのジャンルの作品を描いているときにも感じましたか?
「オカルトについてはとくにそうだろうね。『うしろの百太郎』も含めて、“描かされた作品”ではあると思う。それは霊魂に描かされたのか、壁村に描かされたのか(笑)、物理的な理由はわからんけど、とにかく“描かされた”。だから、たぶん俺はもうじき死ぬだろうけど、死んだらいいところに行けるだろうと思ってるよ。
……(絶句)。
「人間、死んだらなにもなくちゃうわけじゃないんだよ。『恐怖新聞』にも描いてるし、『百太郎』にも描いてることだけど、ただ肉体が滅びるだけで、魂は残るわけだね。つまり、人間は死んで、次の世界に行くわけだ。
わかりやすく言うと、人間というのは、小学校に入ってる状態。死んで、中学校に入学する、というふうに考えればいい。そうすると死ぬということは寂しいこと、悲しいことじゃなくて、卒業するということだから、うれしいわけじゃん。だって、卒業したら、次の段階の入学式があるわけなんだから。というふうにぼく自身は考えてるし、早く、向こうに逝きたくてしょうがないわけだ。
それなのに、なぜか小学校にずっと留年させられていて、まだまだここにいなきゃいけないのか、って、そんな感じですよ。今回のインタビューでは、そのへんのことを書いておいてほしいですね。
死ぬ、ということは、そういうことだよって。
突き詰めれば『恐怖新聞』なんかでも、手を変え品を変えてそのことを言ってるだけなんだからね」
最後になりましたが、これからの『週刊少年チャンピオン』について一言お願いします。
「そういう四角張った聞き方されると、こっちも公式的なことしか言えなくなっちまうなァ。いやァ『週刊少年チャンピオン』、五十周年おめでとうございます。これからもますます栄えていただきたい──とまあ、こういう質問されりゃァ誰でもこういう答えになるわナ(笑)。
あのね、マンガ家っていうのはね、自分の作品以外には興味がなくって、せいぜい仲間の作品くらいしか読まないもんなんです。俺でいえば、トキワ荘の仲間のものは気になって読むけど、後輩のものとか、さらにそのあとから出てきた人のものは、はっきり言って読む気もしないわけだ。それでも、今でもオカルトを描いてるマンガ家がいっぱいいると聞くとね。……まあ、よかったですなあ、広がりましたなあ、って思うよね」
オカルトマンガも少女マンガも、先生の手がけられたジャンルでは今日も新たな作品が生まれ、新しい読者を獲得しています。先ほどの焚き木のたとえで言えば、つのだ先生世代が起こした炎を、あとの世代のマンガ家たちが守り続けている、ということかもしれませんね。本日はありがとうございました。