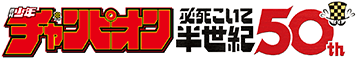2019.10.10
“ブラック・ジャック” 秘話
手塚プロダクション
代表取締役
松谷孝征氏レジェンドインタビュー
週刊少年チャンピオンの歴史に燦然と輝く、手塚治虫先生の名作「ブラック・ジャック」。
手塚先生がマンガを通じて子どもたちに伝えたかった想いを、手塚プロダクションの代表取締役・松谷孝征氏が語ってくださった。

手塚治虫先生が子どもたちに言いたかったこと
惜しまれつつも1989年、60歳という若さでこの世を去ったマンガの神様・手塚治虫先生※の素顔と、その代表作のひとつである『ブラック・ジャック』の秘話を、長年、手塚先生のマネージャーを務めてこられた松谷孝征さん(手塚プロダクション代表取締役社長)からうかがった。
「1972年の年末のことです。当時、マンガ編集者だった私は、手塚から100ページの原稿をいただくために、二か月半くらい手塚プロに泊まり込んでいたんですよ。泊まり込んでいた、っていっても、そこらで飲んだくれてただけですけどね(笑)。そのときに、事務所に単行本があったので、『火の鳥』から『鉄腕アトム』『ジャングル大帝』『リボンの騎士』、そういうのをみんな読みました。もちろん、子どもの頃から『鉄腕アトム』は読んでいました。でも、当時は月刊で8ページかそこらの連載。そのときに初めてまとまった単行本を読んだら、あらためて『鉄腕アトム』や『ジャングル大帝』を通して、手塚治虫は子どもたちにこんなことを言いたかったのか、というのがわかったんです」
その後、出版社を辞めた松谷さんは、手塚先生のマネージャーに転職し、数々の名作誕生の瞬間に立ち会うことになる。そのなかでも、とくに『ブラック・ジャック』の企画は印象深かったと松谷さんは語る。
「子どもマンガに医者が主人公。ちょっと異常ですよね。それと大人、という点もね。
もっとも手塚はね、命の大切さ、尊厳、というのが基本的なテーマですから、医者が主人公というのはいちばん描きやすいし、テーマも打ち出しやすかったんでしょう。
ただ、私も最初は『なんだよ。大人が主人公?』『しかも医者かよ』って思いましたよ。だって、そんな作品はそれまでに全然なかったわけだから。ところが壁さん(週刊少年チャンピオン2代目編集長 壁村耐三氏)は『いいですね。やりましょう』と言ってくれて」
※手塚治虫先生 それまでの漫画の概念を変え、数々の新しい表現方法でストーリーマンガを確立し、マンガを魅力的な芸術にした。その偉大な功績の数々は、ここに書ききれないほど。

寝る間も惜しんでマンガ制作に没頭する手塚先生
当初、3~5話で完結予定だったという『ブラック・ジャック』は読者からの熱烈な支持を得て、打ち切りどころかチャンピオンの看板作品へと成長していく。そして、手塚先生のもとには各社からの仕事の依頼が殺到、手塚先生は寝る間も惜しんでマンガ制作に没頭することとなる。
「なにしろ、いちばんひどいときは、月600ページくらい描いてました。当時の私のスケジュール帳に記録してるので確かな数字です」
単純計算しても一日20ページは描いていたということになる。だが、一年365日、仕事場にこもるのは不可能のはず。松谷氏によれば、手塚先生は「移動中にマンガを描くこともしばしば」だったという。
「電車の中ではね、ぼくを通路側に座らせて、いつも隠れるようにしてマンガ原稿を描いてました。一度なんて、揺れるタクシーの車内でカラー原稿を描いてましたからね。筆洗(筆を洗う器)から水こぼれるくらいの揺れなのに、ササッと描いちゃうんですよ」
しかも、なによりも驚かされるのは、描かれた作品の「量」ではなく「質」である。『ブラック・ジャック』のストーリーのなかには、心を揺さぶられる傑作がたくさん存在しているが、なかでも松谷さんの心に残っているのは第241話の『オペの順番』だという。
「これは、傷ついた議員の成人男性と赤ちゃんと野生生物が出てきて、そのときのブラック・ジャックが選んだ治療の順番は?という話です。この回でブラック・ジャックは議員よりも赤ちゃん、赤ちゃんよりも野生動物の治療を優先させます。全員の命を救うにはそれが最善の方法だったため、そのような行動をとったわけですが、ここまで毅然と対応できるというのは、彼が無免許医師だからできたことなのかもしれません。
手塚がいつも作品に込めていたテーマは《命の尊厳》、それと戦争の悲惨さ、平和の大切さ、そして『ブラック・ジャック』に関していえば《無免許》もそうかもしれません。無免許がいいというわけじゃないけれども、でも、そういうものを通して描きたかったものもあったように思います」

松谷 孝征●まつたに たかゆき
漫画編集者の経験を経て、1973年に手塚プロダクションに入社。手塚治虫先生のマネージャーを務める。手塚先生原作のアニメのプロデューサーも数々手がけた。
日本動画協会の名誉理事。
執筆中、基本的にはストーリーのアイデアについて誰とも相談しなかったという手塚先生。しかし、『ブラック・ジャック』を描いているときにした相談が、大きな騒動を引き起こすこととなる。
「1973年に『ブラック・ジャック』の連載がはじまり、翌年に『三つ目がとおる』(週刊少年マガジンに1974年~1978年連載)やなんかも始まって、メチャクチャな状況になるわけですよ。週刊誌を3本やってる時期もあったりね。だから、あれがどうだとかこうだとかは相談しているひまはなかった。
もちろん描いてる最中にはありますよ。自分で気に入らないと、『どうですか?』とかアシスタントに聞いたり、編集者に聞いたりしてね。編集者や私に聞いても『いや、いいですね』と言うに決まってるんだけど(笑)。
ただですね、ときどき、状況を全然理解してないアシスタントがいるんです。『ブラック・ジャック』を描いてるときでもあったんですよ。一話20ページのうち19ページまで完成してたのに、先生から『どうですか?』ときかれたアシスタントが『うーん、イマイチですね』と答えてしまったときが(笑)。
そしたら手塚は『一度、全部回収してください』って言って、原稿を持って部屋に一人で入っていったきり、いつまでたっても出てこない。それで、一〜二時間したらまったく新しい原稿がバーンと出てきて、『編集者に言って、壁さんにこう伝えてください。明日の朝8時までにあげますから』。それが夜中の12時頃。その場にいた編集者も『そんなこと言えません。冗談じゃない!』。仕方なく私が壁さんに電話したら、壁さんは『ふざけんじゃねえ!』ってガチャンと切ったのね。ガチャンと電話を切るのは、じつはOKの証拠なんだけど(笑) 。そんな思い出がありますね。
『ブラック・ジャック』の連載の最後のほうにも、そういうことがありましたよ。手塚が『もう描く病気がないんです!』と言い出して、どうしようもない状況になったので壁さんに電話したら、『少し寝かせてやれ!』でガチャン(笑)。本当に一〜二時間寝たら元気になってましたけどね」
《マンガはすばらしい》
最後に、週刊少年チャンピオン50周年へのメッセージをお願いすると、松谷さんは優しく笑いながら、こう答えてくれた。
「手塚治虫は30年前に亡くなりましたけど、生涯、必死になってマンガを描き続け、マンガの地位を高めようと必死になってがんばってきました。マンガに批判的なテレビ番組の企画が持ち込まれると『マンガ家で、なかなか口が上手な人っていないじゃないですか。だから、ぼくが出なきゃダメなんです』と、時間を作ってまで出演していました。とにかく必死にやってきて、昔は『マンガなんて……』と言われていたものが、いまや日本を代表する文化になりました。
子どもマンガはもちろん子どもたちのためのものだし、でも大人も納得するものを描かなきゃいけない。だから一生懸命に作品を作り、そのほかのこともいろいろ一生懸命やって、とにかく《マンガはすばらしい》ということを手塚先生はアピールしていました。私たち手塚プロも、その精神を引き継いでやっていかなきゃならないし、週刊少年チャンピオンにもがんばっていただきたいと思います。
海外のマンガのイベントも、いちばん最初の頃から手塚先生は行ってるんですよ。出国する前には、いつもあちこちの編集長に声をかけるんです。『すごいですよ。こっちで言えば文部大臣みたいな人も来るんですよ。一緒に行きましょうよ』って誘っても、『いやあ、海外でマンガなんて売れませんよ』って断られていました。もう40年近く前の話ですけどね。それがね、いまやこんな活況になったわけですから。そういうマンガの歴史とともに歩んできた50年ですよね、手塚も、週刊少年チャンピオンも。だからこそ、いまの編集の方々にはがんばってほしい。手塚をはじめ、大勢の方が関わって、せっかくここまでやってきたんですから。
いい時代もあっただろうし、いまは紙媒体全体が厳しい状況かもしれないけれども、どんな状況でも決してくじけることなく、週刊少年チャンピオンにはさらに次の50年を目指していってほしいと思います」

《週刊少年チャンピオンに掲載された
手塚治虫先生の作品》
「ザ・クレーター」「やけっぱちのマリア」「アラバスター」「ミクロイドS」「ブラック・ジャック」「ドン・ドラキュラ」「七色いんこ」「プライム・ローズ」「ブッキラによろしく!」「ゴブリン公爵」「ミッドナイト」など。